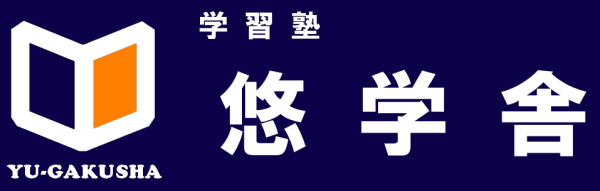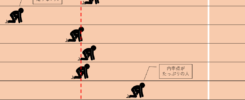「勉強の仕方が下手だなぁ」と思う生徒の特徴のひとつに、
身についていないのに次々と新しいことに手を出してしまうという点があります。
勉強でいちばん大切にしてほしい心がけは、
「やったことを、できるようになるまでやり切ること」
です。
たとえば、
今日、学校の授業中に解いた問題。
それをもう一度、自分の力だけで手順通りに解けるでしょうか?
45分、50分の授業で学んだことが「理解したつもり」で終わっていないか、確認してみてください。
まず、この基本中の基本を大切にしましょう。
今日学んだことが解けないまま先に進んでも、土台が不安定なまま積み上げているようなもので、いずれ崩れてしまいます。
特に国語・数学・英語といった積み重ねの科目は、間違いなく伸び悩みます。
成績上位の生徒ほど、こうした確認(=復習)をしっかり行っています。
「この単元を今日学校で習ったんですけど、よくわからなくて…」
「昨日塾でやった問題、授業中はわかった気がしたんですけど、家でやってみたらできませんでした。」
上位層ほどこういう言葉が出てくる傾向にあり、こうした言葉が出てくるのは、取り組んだことの理解を深めようとしている姿勢の表れです。
一方で、勉強がうまくいかない生徒ほど、
今日の内容をあいまいにしたまま、次に進んでしまっています。
「理解する」よりも「新しいことに触れる」「難しそうなものが解ける」ことを目的にしてしまうのです。
レベル3や4の問題がまだ完璧でないのに、それを飛ばして真新しい見た目のレベル10の問題を質問に来る・・・
「アンタが気にしないといけないのは、そこじゃない。」
――これもよくあるパターンです。
本当に力になるのは「やったことをできるようにする」こと。
「あいまいなまま先に進む勉強法」を続けている状態で、新しい分野にどんどん手を出しても、できるようになるはずがないのです。
今日の授業内容を、きちんと説明・再現できるようにする。
課題で取り組んだものを理解しきる。
この積み重ねが、本当の意味での「学力」を作っていきます。
“新しいことに触れる”より、
“昨日の自分を超える”こと。
勉強のやり方が上手くなりたければ、
この意識はしっかり持っていてほしいものです。