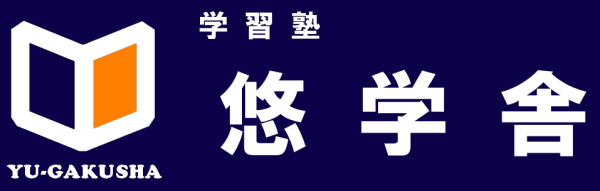こんばんは、塾長の一井です。
先日、情報収集も兼ねて、他塾の先生方とご飯を食べてきました(´ー`)
海稜高校の1期生の話題や、市立3校の合併校である姫路市立高校の志願者の状況だったり、そんな話をしつつ、塾のシステムの話になりまして・・・
『一井さんのところは、
授業する先生とは別で自習対応できる人が常駐しているところが凄いわ。
いつでも対面で質問できる環境はホンマに手厚い。
なかなか真似できんから、もっと外部にアピールしたらいいのに。』
なんてことを言っていただきましたので、ブログにしてみました(´▽`*)
悠学舎の塾の何が凄いか?他塾の先生の見解としては、こんな感じです。
『経営効率を考えれば、手の空いている講師を自習対応のためだけに常駐させるのは非効率であり、むしろ同じ時間にもう1コマ授業を組んだ方が売上につながる、という考え方が一般的。
多くの塾でも自習は推奨されているが、講師が授業に入っている時間帯には対応できないことも多く、自習対応専任の講師を配置するのは人件費の面から現実的ではない。
そもそも、どの教科の質問にも柔軟に対応できる人材を確保すること自体が難しい。』
・・・
そうなのです!
塾生にとっては当たり前ですが、
『いつでも対面で質問できる環境』ってなかなかないのですよ!
まず、悠学舎は授業以外の時間帯も自習し放題の塾です。
平日は16時~22時、
土曜日は13時~22時で使用可です。
しかも!
授業中であっても1人は手が空いている講師がいるので、いつでも質問対応が可能です。
自習中の「わからない…」をその場で解決できる最高の環境です。
どれだけ自習に来ても、質問を何問しても、追加の費用は一切かかりません。
どうしてこんな仕組みにしているかというと、
それは、学力は自学自習を通じて身についていくという考えからです。
子どもたちが一番成長するのは授業中ではなく、自学自習の時間。
その「成長する瞬間」にしっかりサポートを入れたいから、手の空いている講師が常駐しているのです。
授業だけで賢くなるなら、学校や塾の授業を受けていれば解けるようになってるはずでしょう。
でも実際には、同じ授業を受けても「解ける子」と「解けない子」が出てきますよね。
授業とは、新しい知識を「仕入れる場」にすぎません。
あくまで仕入れるだけなので、授業中に使いこなせるようになれる子は多くありません。
この段階では『知っている・聞いたことがある』程度ですね。
仕入れた知識を実際に使ってみるのが自学自習の場。
実際に授業で仕入れた知識を使いながら問題を解いてみて、「知っている→使える」に変えていく過程を積み重ねていくことで、ようやく実戦(テスト本番)で使えるようになります。
実際に宿題をやっている時に「あれ?授業で習ったはずやのに解けない。どうやるんやっけ?」
こういった状況に陥っている人は決して少なくありません。
学習意欲が高い人は「明日絶対に学校の先生に聞く!」と決めて、何らかの目印をつけて実際に質問するところまでできるので、翌日には解決して解けるようにできますが、そうじゃない子はそれができません。
では、聞きにいかない子はどうなるのか?
解けないままです。(当然ですね。笑)
宿題をしている瞬間は悩んでいますが、
「何かわからんけど、まぁいっか。」「また今度、先生に聞こう。」に変わります。
(そして、その「今度」は二度とやってこないか、テスト前日だったりするのです。)
『鉄は熱いうちに打て』と同じです。
学習意欲がそこまで高くない子で「翌日にわざわざ学校で先生に質問する」はできなくても、「今、目の前にいる人にとりあえず聞く」ならできる子はたくさんいます。
「わからない」⇒「じゃあ今すぐ解決しよう!」
これが一番効率が良くて、面倒も少ないのです。
自習に来ていれば、それが出来るのが悠学舎の凄いところです!
夏休み中、授業以外でも積極的に自習に来て、うちの塾の良いところを最大限に活用してくれていた塾生もいましたが、伸び悩んでいるのに、全然自習に顔を出さなかった人も一定数います。
正直、もったいない。
伸び悩んでいるなら、疑問に思ったことをすぐに質問できる環境に身を置いてお勉強するのが得策だと思いますよ。
結局のところ、その小さな疑問を放っておいた結果、解けないが積み重なっているわけですから。
他の塾の先生が「すごい」「手厚い」と言ってくれるような仕組みが悠学舎にはあります。
活用してくださいな( `ー´)ノ
では、本日はこの辺で!